以前に読んだ「学力の経済学」でもよく取り上げられていた、ノーベル経済学賞受賞者でもあるジェームズ・J・ヘックマンの著作である「幼児教育の経済学」を読んでみたので紹介します。
前回の記事はこちら
日本の教育に対する著者のため息が聞こえてくる「学力の経済学」 – 脳内ライブラリアン
ジェームズ・J・ヘックマンの研究
本書は3つの内容から構成されており、①ヘックマンの研究②専門家からの反論③ヘックマンの再反論という順番となっています。
ヘックマンの主な研究は「学力の経済学」の記事で述べたペリー就学前プロジェクトともうひとつアベセダリアンプロジェクトというものがあります。
アベセダリアンプロジェクトは1972年-1977年に出生したリスク指数の高い家庭の恵まれない子ども111人を対象にし、実験開始時の対象者の平均年齢はなんと生後4.4カ月だったようです。
介入の仕方がまた手間が大変かかっており、子ども3人あたり1人の教師が担当となって、家庭学習の進め方や勉強のカリキュラム作成、親の仕事探しの手伝いやら子どもの送迎やら育児のみならず親の補助までやっていたようです。この毎日の介入は5年間続けられました。
結果としては30歳時点までフォローされており、介入群はより学習面でも生活面でも良い成果を上げ続けました。(詳細は本書中にはあまり書いてありませんでした)
このヘックマンの研究結果からの主張は冒頭で述べられており、以下の3つになります。
1、人生における成功は認知的スキルのみでは決まらず、非認知的な要素、つまり、根気強さ、注意深さ、意欲、自身といった社会的・情動的性質が重要
2、認知的スキルも非認知的スキルも幼少期に発達し、家庭環境に左右される
3、幼少期の介入の効果は永続的であるため、幼少期の教育に力を注ぐ公共政策によって問題が改善できる
要するに、幼少期教育の効果は永続的であり、効果も高いので、あとから何かを再分配するやり方よりもはじめにやっておいたほうが効率がいいよ、ってことですかね。
反論
本書が面白いのは中間部分に教育や経済学、哲学などの専門家から浴びせられるヘックマンへの反論です。概ね幼少期の教育が良いことは認めながらも皆さん批判をしっかりしてきます。
挙げられていることの例としては
・家庭環境を重視しすぎているが他にも学校など子どもが関わる人はいるの
・父親の役割に触れていない
・小規模研究に過ぎず、実際の大規模研究では幼少時介入の結果が出ていない
・思春期からの介入ももう少し考えた方がよいのではないか
・幼少期の教育の仕方によっては白人中流階級の考え/習慣の押し付けになるのではないか
などなど。
これに対する再反論を最後の章で展開していきますが、この本でわかりにくいのは反論も再反論もページがそこまで多くないので、これだけを読んでいてもどちらが説得力があるのか判断しにくい点です。元論文読めっていう話なんでしょうが、さすがに一般向けの書籍とするならちょっとそこまで要求するのは厳しいですね。雰囲気はつかめるんですが。
ただ、反論している側の論点をみていると、「確かに」と納得できることも多く、わずかながらの実験やデータではわからないことが多数あることに気づかされます。いかに良い教育というものが評価しにくく、難しい問いであるか、を実感させられます。
タイトルとの乖離
読み終えてみて思ったのは「幼児教育の経済学」というともっと幼児教育についての経済的なデータを紹介しつつ論じていく本かと思っていました。むしろ幼児の教育についてどうすべきかを経済のみでなく総合的に議論した本という印象でした。確認してみたところ、原題は”Giving Kids a Fair Chance(拙訳:こどもに公平な機会を与える)”でした。こっちのほうがしっくりくるじゃん!タイトル詐欺じゃん!と思いました。出版的には日本語で売れるタイトルにしたかったのかわかりませんが、今後訳書を買うときは原題もチェックしようと思った次第です。



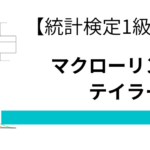




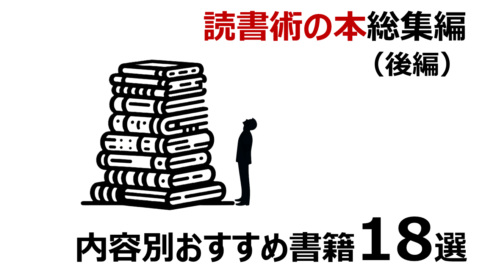

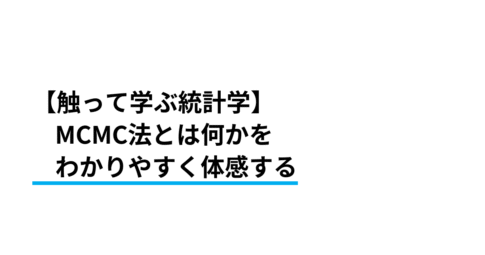
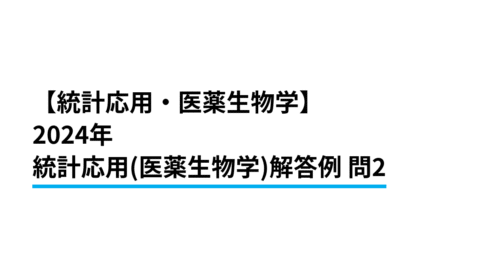
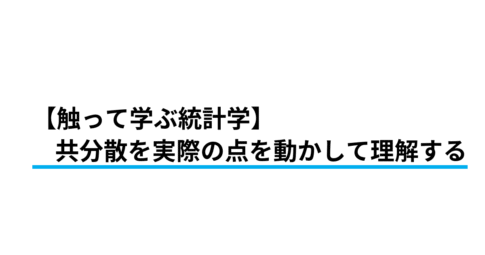
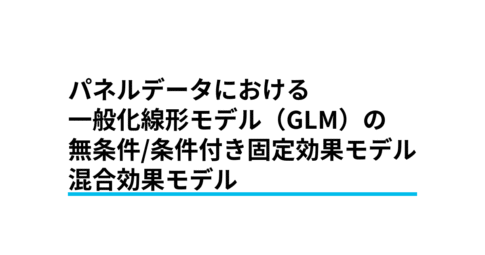
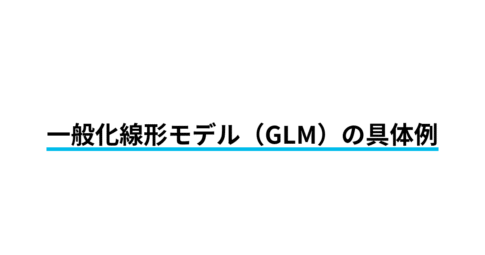
コメントを残す