以前から本はよく読んでいるものの、ごくたまにしか書評・レビューは書いてませんでしたが、notionやGoodnoteに内容をまとめていく上で、もっとブログなどにもアウトプットした方が頭に残りやすいし、内容も整理されやすいなと感じ始めました。そこで備忘録がてら面白かった本を数冊抜粋して時々記事にしていこうと思います。
毎回一冊で長い記事を書くのも大変なので、数冊まとめて短い文で紹介するものと、一冊しっかり書くものと分けていきます。
興味のある分野は医療・言語・哲学・統計あたりなので(数学的な統計の教科書はちょっと毛色が違うので分けようと思います)その辺りの本を中心に分野を分けながら書いてみます。
今回は『ADHD大国アメリカ つくられた流行病』『リスク化される身体:現代医学と統治のテクノロジー』『科学は不確かだ!』の三冊を紹介します。
『ADHD大国アメリカ つくられた流行病』
アラン・シュワルツ著、黒田章史、市毛裕子訳
精神疾患の一つとして認識されているADHD。それがいかにして広がりすぎてしまい、中毒性のある薬剤の害が生じているかを描いたルポルタージュ。
著者のアラン・シュワルツさんは医療系ジャーナリストでアメリカンフットボールのプロリーグであるNFLにおけるconcussion(脳震盪)の問題を描いた記事でも有名になっている人です。合わせて一時期、臨床系ジャーナルでもフットボールによる頭部外傷の論文が多かったように思います。
キース・コナーズというADHDの第一人者が、自身の作った評価尺度が誤った形で拡大し続ける様を憂い、取材に全面協力しています。
内容としてはADHDの概念の変遷から、学生時代に診断を受けた個々人のケース(最悪のケースとして薬物依存から自殺に至った例も)、製薬企業による過剰な広告展開と一部を加担する医師、教育現場を詳細に、臨場感の伝わる文章で綴っています。
本書は決してADHDの疾患概念が根本から間違っているというわけではなく、あくまで疾患概念が濫用されていく様を事実を踏まえて俯瞰することを目標としています。診断基準が主観的な印象で変わりうる疾患というのはいずれも同様の経過を辿る可能性があって、例えば専門書ですが『科学的認知症診療 5lessons』をみると、アルツハイマー型認知症の認知症の中での割合が平成11年頃から急激に増えていることが指摘されています。
これは偶然にも認知症の治療薬とされる薬剤(と言ってもそこまで効果が高いわけではない)が発売され始めたタイミングと重なります。もちろん他にも介護保険制度の関係や認知症に対する疾患知識の普及・啓発運動などは関連している可能性があることを指摘されていますが、やはり薬剤の登場は大きな影響を与えているように思われます。高齢化により認知症が増えるのは当然ですが、アルツハイマー型認知症の割合だけ極端に増えるというのは不自然でしょう。
同じような疾患であれば同様の傾向は常に現れうること、薬剤の有害性は容易にはみえにくいことは肝に銘じておく必要があります。
『リスク化される身体:現代医学と統治のテクノロジー』
美馬達哉著
医師でありながら医療人類学、医療社会学を専門とする著者がリスクの概念を多面的に捉えつつ、現代医学を見直した一冊です。
リスクというと科学的に、客観的に捉えられた確率であると思われており、正しくリスクを認知して「正しく恐れることが大事」だなんて言われがちですが、本書はそうしたリスク観ではなく、もっと多様化し実在なく揺らぐものとしてリスクを論じています。それは主に社会的・文化的な意味づけによって変化したり、複合的で予測困難であったりする点です。
本書の冒頭では以下のような例が挙げられています。子どもは学校内で亡くなるのと交通事故で亡くなるのでは後者の方が当然多く危険性が高いと言えます。ところが、学校内で子どもの死傷者が出ると大きく報じられます。これは学校は本来安全なところである、という社会的な位置づけによるものです。
また、複合的なリスクとは、人工的な介入が増え、それが生み出す副反応を考慮しなければならなかったり、グローバル化によって関係する要素が増えすぎていたりといった点から専門家であっても予測が困難であることを指します。この特徴はCOVID-19の流行を考えると容易に想像がつきます。
医学においては1970年代以降、菌と感染症に代表される特定病因論的な医学から、肺がんとタバコに代表される確率論的病因論(そして多くの場合はこのように一つではなく多因子)へ主たる対象が変化してきており、これらのリスクの特徴と強く関わりがあることがわかります。なお、先ほど例に挙げたCOVID-19は感染症ですが、ウイルスと感染症という病因に問題の主座があるのではなく、感染の広がりと予防という疫学的・予防医学的な点が問題となっているためリスクとの関わりは当然深いです。
本書ではこのリスクが実害よりも遥かに大きく認識されてしまうリスクパニックの概念を新型インフルエンザでのワクチンの害を例にとりつつ紹介し、予防医学がいかように浸透しているかをミシェル=フーコーの生権力を用いつつ説明、また延々と話題になり続ける医療崩壊についてもよく報じられるものとは異なった視点で描いています。そして最後に2011年東北の大震災におけるリスクの捉えられ方を総合的に評価し振り返りをしています。
さて、ここでミシェル=フーコーが出てくると、ポストモダン思想あるいは構造主義的な思想であって、非科学的な相対主義を謳う本なのではないかと警戒したくなる気持ちが生じます。少し前に紹介記事の取り下げで話題になった『「社会正義」はいつも正しい』などで紹介される行きすぎた相対主義、構造主義は歩み寄りのない孤立した主張となってしまっています。
ただ個人的にはそもそも医学そのものがそこまで科学的ではない側面が多いので、過度な相対主義でなければこうした心配は不要であり、むしろこうした社会学的な観点からでないと捉えられないことが多くあるように思います。本書では手術における清潔・不潔の概念が、どこまでを清潔とするかの線引きにおいて、実は明確な根拠がない部分もあり(もちろん清潔の意味がないとかそういう話ではないです)その意味では呪術や儀式と変わりない点もあることを例示しています。この例だけでなく「個人のリスクは評価できない」「複合的なリスクは予測できない」など特に臨床医学におけるリスクコントロールは不確実性がかなり高いといわざるを得ません。
そのため唯一無二のものとしてではなく、謙虚な形でリスクを捉え、それを正直に伝えていくことのほうがよほど科学的な態度なのではないかと思います。
本書で描かれる分野は多岐にわたっており、その内容についてはまだ不十分と言わざるを得ないので、引用文献はまた追加でいくつか読んでみたいですね。
『科学は不確かだ!』
R.P.ファインマン著 大貫昌子訳
ファインマンは物理学におけるノーベル賞受賞者で、ユニークな人柄が有名です。統計関連の本を読んでいたときにCargo Cult Scienceと題されたファインマンの講演が引用されており、その科学観に興味があったのですが、図書館をふらついていたところたまたまこの著作を見つけて、読みました。エッセイとして有名なのは『ご冗談でしょう、ファインマンさん』でこちらはまた読んでみたいと思ってます。
さて本書は1960年代、キューバ危機の直後になされた3日間の講演を邦訳したもので、「科学の不確かさ」「価値の不確かさ」「この非科学的時代」という題でそれぞれ話されています。
科学の特徴と限界を講演としてわかりやすい内容で語っており、哲学や宗教、政治についても自論を語りながら、倫理的問題は科学の関与するところではないことを明確にしています。2日目にはソ連に対して非科学的なまでにボロクソに語っているところには時代を感じますが、3日目にはこうした権威も科学的ではないことを言いますよという伏線だったといってみたり(本当か?)しています。人柄と時代を感じさせるところではありますが、権威があるからといってなんでも真に受けない方が良いというのはその通りかもしれません。

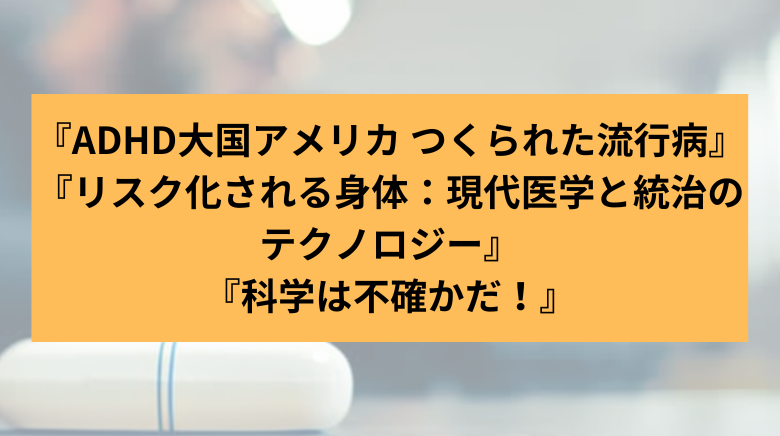

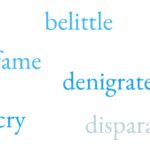



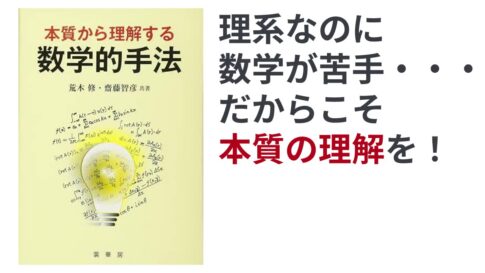


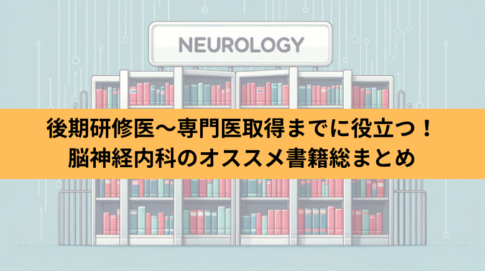

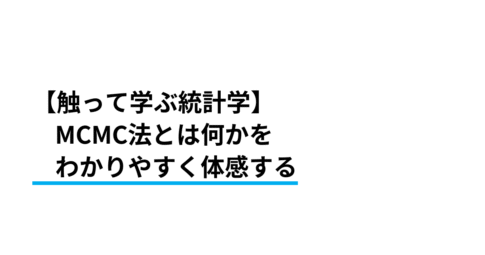
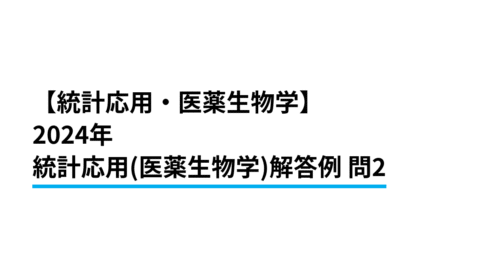
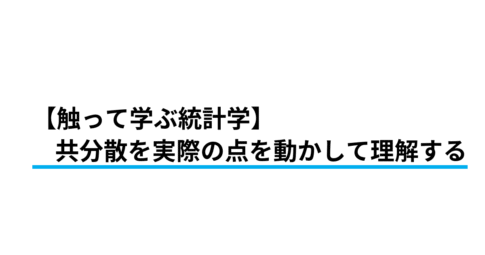
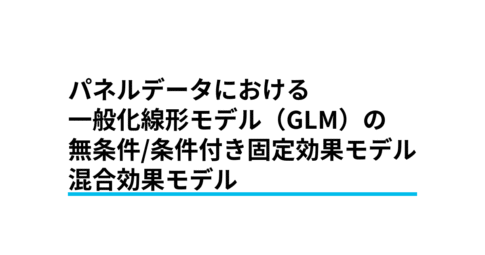
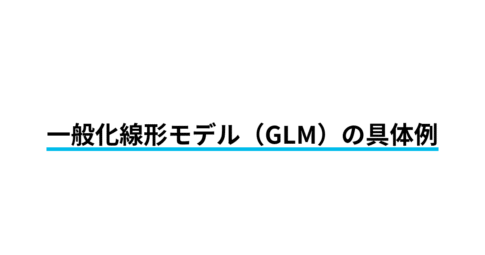
コメントを残す