カルバック-ライブラー情報量〜赤池情報量規準(AIC)までの概略をわかりやすく②【統計検定1級対策】
引き続いて赤池情報量規準への道のりを進めていきます。続いてAICの意義は前回説明したので、カルバックライブラー情報量の説明をしながら、なぜAICの式が成り立つのかについて、迫ります。 前回の記事はこちら カルバックライブ...
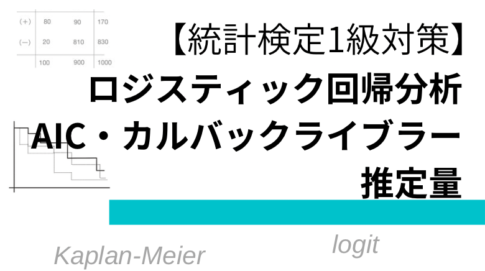 統計
統計引き続いて赤池情報量規準への道のりを進めていきます。続いてAICの意義は前回説明したので、カルバックライブラー情報量の説明をしながら、なぜAICの式が成り立つのかについて、迫ります。 前回の記事はこちら カルバックライブ...
 哲学
哲学今回の記事ではニーチェの思想にとって大事な、どんな人であったかを振り返ってみます。 前回記事はこちら 【生きる目的が分からなくなってしまった人へ】フリードリヒ・ニーチェの思想① – 脳内ライブラリアン ...
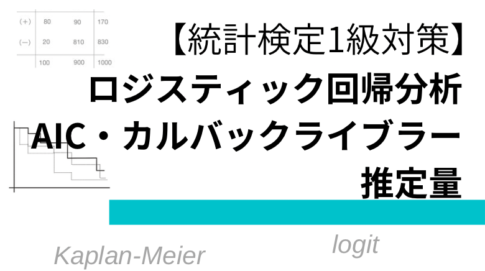 統計
統計今日は久々に統計の話です。今まで何度も本を読んだけれど、何回読んでも理解が届かない赤池情報量規準について、精一杯手の届く範囲で説明してみようと思います。 導出は統計検定1級の範囲外で、教本にも記載がないので、細かい導出は...
 哲学
哲学「神は死んだ!」に代表されるセンセーショナルな言葉で、今なお影響を与え続ける19世紀の哲学者、ニーチェ。今回からはニーチェを紹介しようと思います。 ニーチェはその刺激の強さゆえに、というところがあるかもしれませんが、...
 哲学・倫理・医療社会
哲学・倫理・医療社会以前の記事で勉強と記憶において論理力というのは重要であることを書きました。 medibook.hatenablog.com 哲学の本を読むにせよ、医学論文を読むにせよ、あるいは書くにせよ、論理力は基本であり、必要な能...
 哲学
哲学現象学の方法論と現象学が生まれるまでの流れを今までにみてきました。今回はその応用方法を一度考えてみようと思います。 前回までの記事はこちら 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・フッサールと現象学② – ...
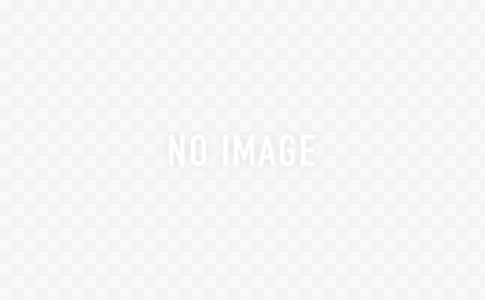 哲学
哲学前回記事では現象学の中心となる思考スタイルである「現象学的還元」について紹介しました。 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・フッサールと現象学① – 脳内ライブラリアン 今回はその提唱者であるエドムン...
 書評
書評現象学はエドムント・フッサールに始まり、ハイデガー、メルロ=ポンティ、サルトルと幅広く使われていった学問であり、思考のスタイルです。 こちらの記事で内容について紹介しています。 【意見対立の解消に役立つ】エドムント・...
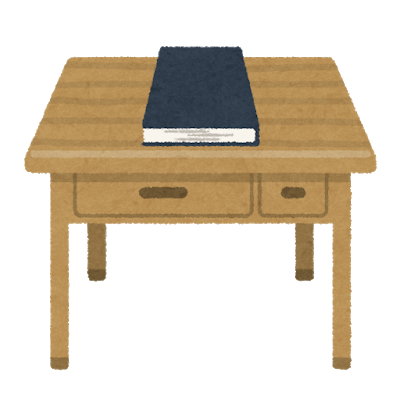 哲学
哲学内容が難しすぎて、本を読んでから書き始めるのに時間がかかりましたが、哲学の話のまとめをまたやってみようと思います。 かなり現代に近づきますが、今回は「現象学」についてです。 「現象学」ってなんやねん、とまず思った...
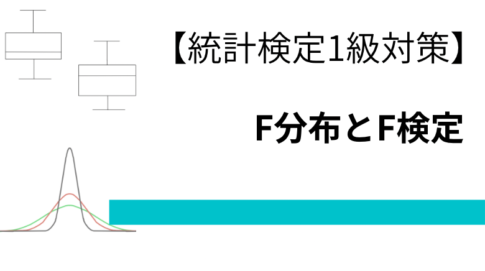 統計
統計前回はt分布についてやりましたので、今回はF分布とそれに関連したF検定についてやっていきます。 目次: F分布とは F分布というのは、分母も分子もカイ二乗分布に従う分数の分布です。具体的には自由度mのカイ二乗分布 \[\...
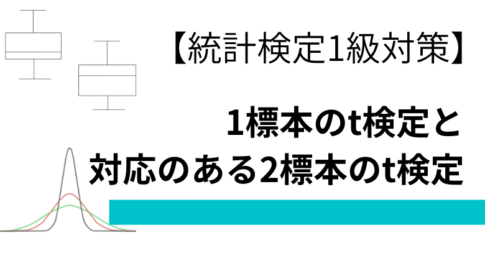 統計
統計さて、過去問解きつつも、全くもって受かる気がしてこない統計検定1級ですが、引き続きあがいていこうと思います。というかコロナの影響で6月の検定やられてないのですが、果たして11月はやるんでしょうか。 今回はt分布の確率密度...
最近のコメント