9/17に出版されたデビッド・A・シングレアの本『LIFE SPAN』を読みました。
著者は長寿遺伝子(活性化させることで寿命が延びる遺伝子の総称)のひとつである、サーチュイン遺伝子の研究者で、人間の寿命をいかにして伸ばすかを研究している方です。
こうした基礎医学と呼ばれる領域は、得てして臨床医が用いる臨床医学とはまだギャップがあるので、実際の人間に応用されるにはまだ距離があることが多いです。ただ、この本に書かれている知見や考え方からは、これからの医学の大きな方向性を感じさせられたので、医師の視点から本の内容と感想についてまとめてみます。
目次:
研究結果をただ示した本ではない
本書は大きく分けて、第1部で「今までの研究結果について(過去)」、第2部で「現在の知識(現在)」、第3部で「知識を用いてのこれから(未来)」を語っています。
まず、過去~現在の研究結果から、人間の寿命を延ばすことが可能であると筆者は主張します。これはユヴァル・ノア・ハラリが『ホモ・デウス』で述べていたように、immortal(不滅)ではなくamortal(不死、事故などでは死ぬことがある)を目指すものです。
このあたりまでは、よくある研究結果を一般向けに書いた本という感じです。
ただ、単純にそれだけではなく、未来において、現在の人がもっている「”老い”を仕方のないものとする」「高齢者=身体・精神的に能力が落ちており社会の役には立たない」という主張を捨てて、新しく切り替えるべきだという思想的な主張を持つことが本書の特徴だと思います。
そもそも「老い」の原因は何か?
なぜ人が老いるのか。この疑問に対して筆者は研究を進めてきました。第一部ではこの内容が語られます。
筆者が紹介しているのはマグナ・スペルティスという仮説。これは大まかにいうと、2つの遺伝子同士の活性化の有無によって、細胞の生殖・交配が支配されているというものです。具体的に、遺伝子AとBを用いてモデルが説明されます。
まず、ある遺伝子Aは細胞の増殖にブレーキをかけるもので、周囲の環境がいい時は遺伝子Bからつくられたタンパク質がこの遺伝子Aを止めるので、細胞の生殖・交配が行われます。逆に周囲の環境が悪い時(DNAがダメージを受けるようなとき)は遺伝子Bからつくられたタンパク質が損傷したDNAの修復を行い、細胞の生殖・交配はストップします。
こうした遺伝子は太古の生物から人間にまで引き継がれ、種類は増えますが、現在も人間の「老い」に関連していると考えられています。
この遺伝子がサーチュイン遺伝子やmTOR, AMPKといったものであり、これらをうまくコントロールすることで、DNAの損傷を防ぎ、「老い」を防ごうというのが筆者の主張になります。
「老い」は病気である
筆者は上述の研究の結果から「老い」は防げるもの、と考え、病気として捉えるべきであると主張します。
世界全体でみても、かつての病気と言えば感染症が主体で、なってから治療して治すもの、というイメージが強かったと思います。実際医学の進歩に伴ってそういった病気(人と人との接触で起こるcommunicable disease)はかなりの割合が治療されるようになりました。
ただ、現在高齢化で問題になっているnon communicable diseaseは、それとは異なり、治療してぱっとよくなるものではありません。代表的には、がん、心血管疾患、脳血管疾患、認知症などですが、どれも高齢になればなるほど起こりやすく、一回治せたようにみえても体のダメージは戻らないので、再発します。また認知症のようにそもそも治らないものもあります。
このcommunicable disease→non communicable diseaseへの推移は主要な医学ジャーナルであるLancet誌に載せられている世界の疾病負担割合の研究(Global burden of disease)からも明らかで、世界全体における主要なトピックと言えます。
Lancet Global Burden of Disease
この問題をどうにかするには、その場での治療技術の発展もひとつですが、これはあくまでモグラ叩きのような「出てきてから叩く」戦法であり、「老いる」という根っこを抑えることのほうが有効だというのが筆者の主張となります。
もちろん、なってしまった人に治療する手段も発展は必要だと思いますが、可能なのであればもっと早くから「老い」を予防していくことのほうが、楽であり、本人にとっても望ましいと思います。
また、大規模な予防で助けられない希少疾患はどうなのか、という意見もあると思います。これも負担の大きい「老い」による疾患を防ぐことで、医療費の余裕をつくり、希少疾患の治療に財源をシフトしたり、希少疾患の介護者が健康を保つことで、介護の場面でも余裕を与えたり、良い影響が期待できるのではないでしょうか。
医療者はあくまで、明らかな病気になった人を治すことが現在の仕事の主体であり、それ以上の権限はありません。なので、老いを予防するためには医療者だけでなく、一般的な人達の考え方が変わること、もしくは医療者の仕事が変わること(予防的な介入を増やす)が必要だと思います。
「 老い」は自然なことなのか
老いは病気であると主張する以上、「歳だから仕方ない」「老いるのは自然なことだからしょうがない」という考えに筆者は反対です。老いも、人間なら何とかできるものとして扱います。
こう言うと科学者のとる傲慢な姿勢だと言われそうですが、「老い=自然なこと=良い」という図式で思考停止することには個人的にも反対です。「自然=無条件に良いこと」としてできるだけ医療に関わらないことを勧める本や健康療法は多数あると思います。そこで言われる「自然」って何でしょうか。人間にとって最も「自然」だったのは、狩猟採集をしていた何万年も前の遠い時代のことで、今の食事や生活習慣、行動には「自然」なんてものはほとんど残っていません。元々存在しなかった医療や処置は自然でないから受け入れない、としても、それ以外の自然でない生活の問題があまりに多いので、体がよくなるとは到底思えません。
ただ、実際現在の医療では老いて病気になってしまった状態から改善する方法はないので、「自然」という言葉に頼らざるを得ない面もあります。脳卒中でご飯も食べられず、疎通もとれなくなった高齢の患者さんの家族が「胃ろうや人工呼吸器といった処置はせずに自然のままで見たいです」と言われた場合には共感します。この時の「自然」は「理想」として使われるのではなく、ある種の「諦め・受け入れ」として使っていると思います。これがいつの間にか「理想」に入れ替わってしまうことを懸念しています。
第3部ではこうした「老い」に対しての固定概念を払拭すべく筆者は主張を繰り広げますが、尊厳死に関して強く賛成していることはちょっと受け入れられませんでした。本書中では健康寿命が延びて高齢者が増えた際に、健康に生活できなくなった際に、そうした選択肢を与えるべきではないか、としていますが、それとこれとは別な問題のように思います。高齢になるまで健康に生活して、体の調子が崩れたら尊厳死が選択肢となる、というのは「何らか体がうまく機能しない人は死を選ぶ」という思想にあまりにも誘導されてしまうようで、周りからそうした圧力がかけられるようになるのではないかという点で不安があります。
現時点での長生きをする方法は
ちなみに筆者が実践している長生きための生活習慣が本書の終わりに書いてあります。NMNのサプリを飲む、メトホルミンを飲む、トレーニングをする、間欠的に断食をする、などなどです。ただ筆者も述べているように、筆者自身は医者ではなく研究者であり、実際的な指導をしていく立場ではありません。いくつかの内容はあくまで基礎研究からの結果であって、大規模な臨床試験として証明されたわけではありません。
また、筆者は自身の遺伝子解析や定期的で詳細な採血検査をもとにやることを組み立てているようなので、一般的な人では良く調べて勉強してからでないとわからないですし、まして、普通の医療機関の保険診療ではできないと思いますので、やすやすとマネできたものではありませんでした。
参考ぐらいに留めて、本当に意味があるかどうかは勉強したうえで行うことをお勧めします。間違っても、本に出てきた用語を使っただけのサプリメントを盲目的に買うことは避けて欲しいと思います。運動とか砂糖・塩分のとりすぎを避けるとか一般的なものは効果もほぼ証明されてますし、確実に良いですけどね。
かかりつけの医師にこのあたりの質問をしたとしても、人によるとは思いますが、実際明確な答えには困ると思います。医師の側も今の教育では診断・治療に重きが置かれていて、こうした予防医学・生活習慣の改善といった内容はほとんど教えられていない(教えられたかもしれないけど記憶に残らず、実際に使う場面も十分でない)ので、、、。
自分も決してそういった知識が豊富にあるわけではなく、本格的な予防的医療を始めるには、まだまだ医療を与える側も受ける側も、体制と知識が足りないなと気づかされた一冊でした。





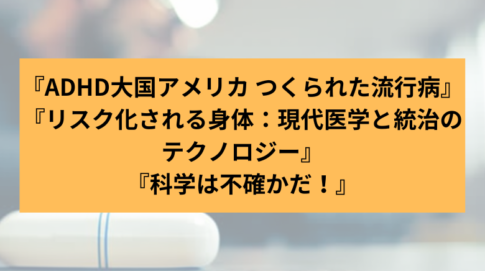

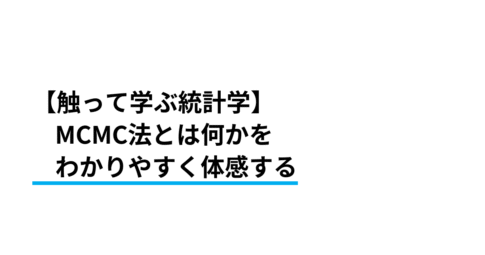
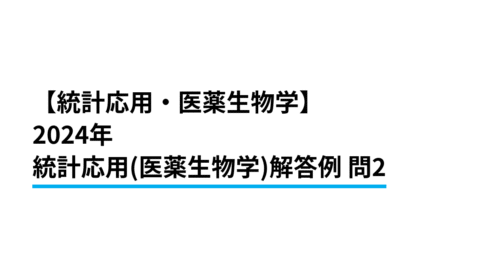
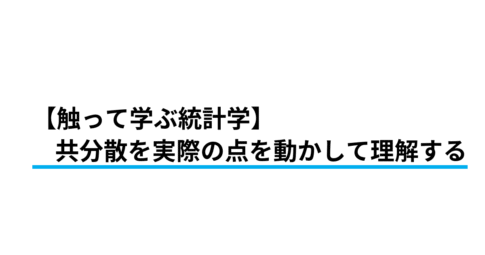
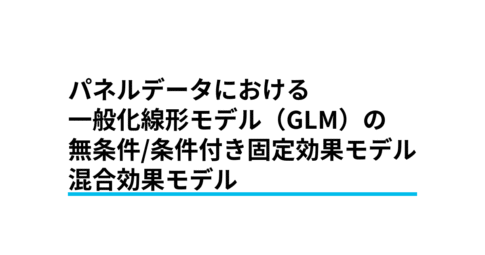
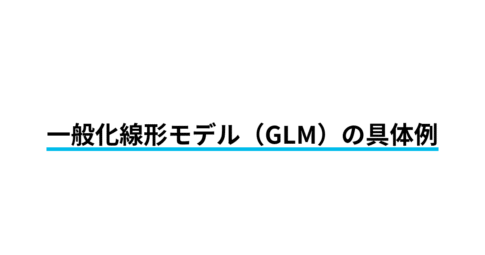
コメントを残す