最近また本を読む時間が増えてきて、notionなんかを使って整理したり、記録するのが楽しくなってきたのでtwitterやブログの方にも感想をあげていこうと思います。
今回は鈴木哲也著『学術書を読む』についてのレビューをしていきます。
専門外の知識が欲しい
このブログを元々始めたのは臨床医として働いていく中で、医学の問題がいかに多くの分野が絡み合う領域であるかを否が応でも自覚させられ、もうちょっと周辺分野を学びたいと思ったのがきっかけでした。
臨床試験に関するところで統計学との関連は当ブログでも一番扱っているところですが、経済、政治、哲学、倫理学、化学、遺伝学などなどまあ挙げればキリがありません。おそらくこのブログをみてくださる方は医学以外だと統計学に興味がある方が多いと思うのですが、そうした方々もそれぞれ統計以外に専門がある人も多いのでしょう。
では、こうして複数にまたがる専門外の分野をどう学ぶべきなのか。そしてなぜ学ぶべきなのか。
そんな疑問にヒントを与えてくれるのが今回紹介する一冊『学術書を読む』です。
この本の中では、学術書を出版する側である京都大学学術出版会の専務理事・編集長の著者が、学術書を読むことについて議論を広げていくのですが、一般的な読書系ハウツー本とはちょっと違います。
なんとなく読書本だと「本の選び方」や「本の読み方」が内容の中心となるイメージですが、この本では「なぜそうした本を読む必要性があるのか」にむしろ重きを置いており、その必要性から「知のあり方」まで遡っている点が特徴的です。
そこから読み方や本の選び方を導き出すような流れとなっており(分野が多岐にわたるためか、むしろ読み方や選び方はあまり具体性はないです)、あくまでそちらはオマケという印象を受けました。
しかし、確かにこの「専門外の学術書を読む必要性」を意識することでどう読むか、何を読むかが変わってくるように思うのです。
なぜ専門外の知識が必要か
本書はまず第1部で専門外の学術書を読む理由を挙げていきます。冒頭で挙げられるのは筆者の主張する「現場の哲学」の必要性です。
「現場の哲学」とは?
「現場の哲学」とは要するに多岐の専門や職業、社会的立場にわたるような問題を解決する場合に必要となる考えのようなもので、例として「津波や豪雨に対する防災」「iPS細胞による治療」などが挙げられています。具体的に「iPS細胞」で言えば、細胞生物学をベースとして臨床応用では各種の疾患の知識に、統計学の知識が必要で、こうした治療を行うには倫理学における問題も関わります。これを解決しようとするには複数の専門領域への理解が必要であり、それを筆者は「現場の哲学」と呼んでおり、それが得られるのは学術書だとしています。
専門領域の知識を構成するのは論文とそれを掲載する学術雑誌(ジャーナル)となるわけですが、なぜこれらでは「現場の哲学」が得られないかというと、理解するには各専門分野の背景知識がなければ難しいことが多いため、としています。また、論文は専門家内での業績評価の対象となっており、一般向け・専門外の人向けといった枠を越え出ていくことができません。そこで本書が主張するには、学術書が架け橋となる、というわけです。
もちろん学術書にもガチガチに専門家向けに書かれたものもあるでしょうが、そうではないものも含まれる、という意味合いでしょう。
また、これはよく言われる事柄かと思いますが、他の領域の視点も取り入れることで自らの専門に対して「自省」するための視点を得ることができるというのも重要なポイントとされています。
「わかりやすい」は問題?
この「現場の哲学」という概念の必要性をもとに本書で強く問題視されているのは「わかりやすい」というパラダイムが力を持ちすぎているという点です。
上で述べていたように複数領域にわたる問題を解決するための「現場の哲学」は、それぞれの専門内容を、時には時間を十分にかけて正確に説明していく必要があります。筆者が問題視している「わかりやすい」パラダイムの問題点は「きちんと正確に説明されている」という意味でわかりやすいのではなく、本来必要なものまでも切り落として「簡略化」されてしまったという意味のようです。
実際、「わかりやすい」は学問に関連した書籍、動画、ブログ記事(当ブログもそう書いたりしてますね)でとにかく人気のあるワードです。SEO対策としてもウケが良いワードとなっています。「わかりやすい」「簡単」「〜週間でマスター」「〜日でできる」「スキマ時間で学べる(どこかで聞いたような)」など楽に学べるコンテンツは人気がありますし、学び始めようという時には見てしまいがちです。
ですが、その一方簡略化された参考書や動画、ネット記事では誤りが生じやすいこともよく指摘されています。これは物事を簡略して書くというのはつまり、背景知識や論理を省いている点があるということになるので、こうした本質的な理解の妨げとなる誤りは必然的に生じるものだと言えます。
また「わかりやすい」のパラダイムの中で、他にも本書で問題だと指摘されているのは「学術成果が情報化されている」という点です。
本来研究内容というのは学問ごとにある種の知識体系・背景知識があって、その中の一部として位置付けられる研究結果であるはずが、その成果のみが抜き出されて都合の良い「情報」として消費されるようになってしまっているということです。
例えば「何百本の論文を読んでます」「エビデンスに基づいています」というサイエンスライターやメンタリストの本を見ると、そこにはエビデンスという名の切り取られた「情報」が大量に並んでいます。自分が背景知識として持っている医学関連の項目を見ますと、そこで紹介される個々の研究は、実際に応用するにはあまりに無理のあるものが多く、これが多くの人に流布されるのかと思うと悲しく思った記憶があります。
この辺りの「知識」と「情報」の違いについては本書内できっちりとは定義されていないので、あくまで読んだ上での個人的な印象ですが、上記のように一般向けに売れている本で多くはこういった特徴を捉えている気がしてなりません。
こうした「情報」のみの抜き出しはCOVID-19流行下でも盛んで、全体の知識体系の中でなく、一部のデータ・情報を抜き出して紹介していくスタンスは多く見受けられるように思います。結局はそうなると確証バイアスのかかった意見しか出てきません。面倒であっても1からその学問の体系を学び知識を積み上げていくことが必要なのではないでしょうか。
ではなぜこうしたコンテンツが増えてしまうのか。本書では知の評価のあり方にその原因にあるのではないかとしています。
知の評価の数値化
研究領域の知の評価として学術書の記載は外れ、論文数やインパクトファクター、被引用数など数値化されたものが主に参照とされるようになりました。論文数という数値は、客観的に評価しやすいようにもみえますが、そればかり見ていると内容は問われなくなっていきます。
そこで内容を担保するための指標としてインパクトファクターや被引用数があるわけですが、これもあくまで数値であるため、実は色々なごまかしが効きます。
この辺りは『学術出版の来た道』(岩波書店)の第8章「商業化した科学と数値指標」が詳しいのですが、インパクトファクターは「学術誌全体の引用数÷掲載論文数」のため、どれを掲載論文として分母に入れるかをうまく減らしてみたり、被引用数は自国の文献を積極的に引用しまくって増やしたり、いずれも指標として取り沙汰されれば、かえってその意義が歪んでしまうという悲しさがあります。
このような数値という客観的指標が研究者領域でも評価基準として価値をもつようになってしまった結果、社会全体においても情報化・わかりやすさが進んでしまったのではないかというわけです。
個人的には研究者の知識の評価のあり方がそのまま一般社会に影響を与えた、というよりかは研究者も含めた社会全体が同時に変化したと考える方が自然ではないかと思ってはいます。”Four Thousand weeks: Time Management for Mortals(邦訳:限りある時間の使い方)”で言われるような「効率化」が重視された結果、数値的な指標を過度に重視するようになったという考えの方がそれらしいのではないでしょうか。いずれの原因であってもこうした数値しか重視できない状態は不健全だとは思います。
まとめ
「学術書を読む目的」を今学術と社会全体が抱える問題は何なのかという視点で紹介した一冊でした。知識のあり方について論じている点が面白いのですが、紙面の都合かそこまで詳細に論じているわけではなく、細かい点をもっと詰めたくなるような内容ではありました。
なお、今回のレビューでは全く触れてませんが、本書では第二部でこの目的に基づいた具体的な本の選び方も紹介されています。ただ学術書といってもジャンルが広すぎるので、これを読んだだけでどのジャンルの学術書でもうまく選べるというものではなく、一番大事な読む目的に基づいて自分に必要な本を探す努力が必要そうです。

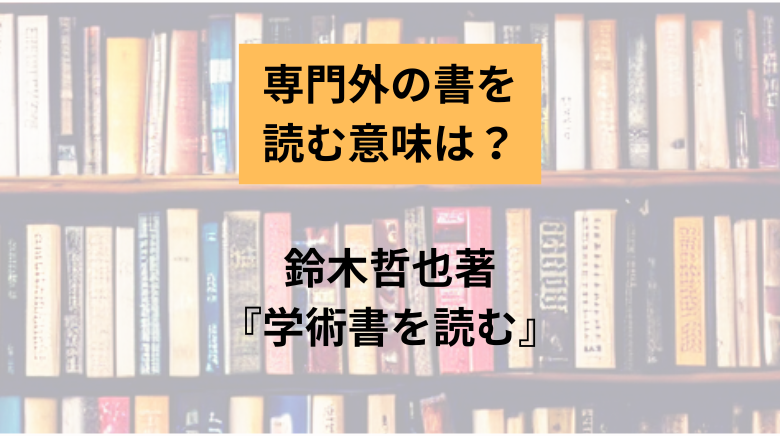

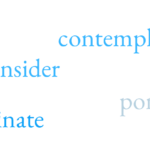
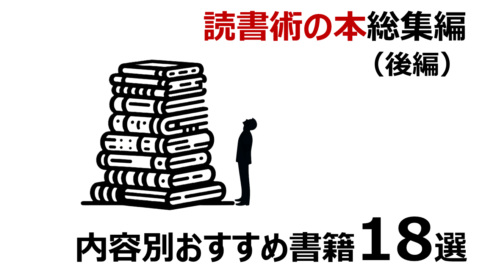
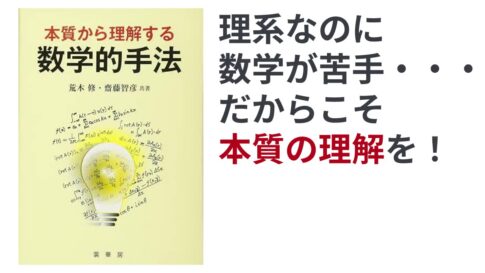



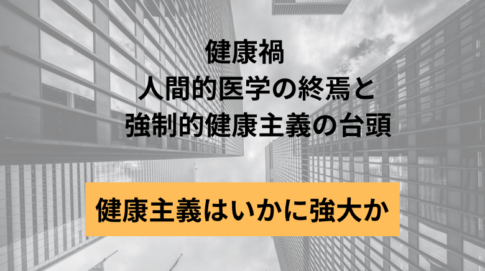

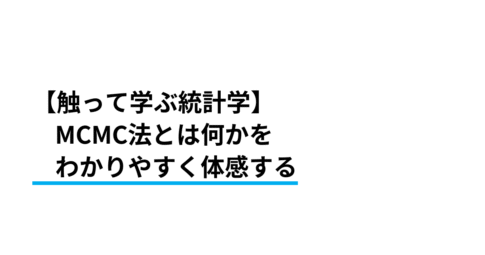
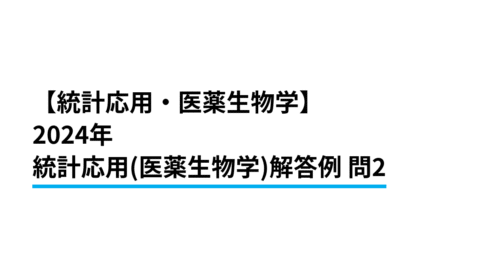
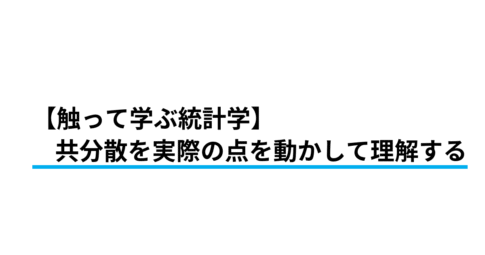
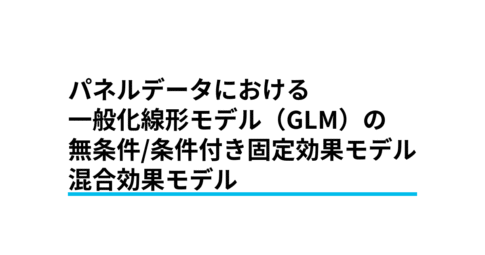
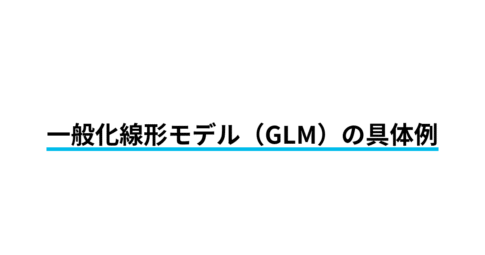
コメントを残す